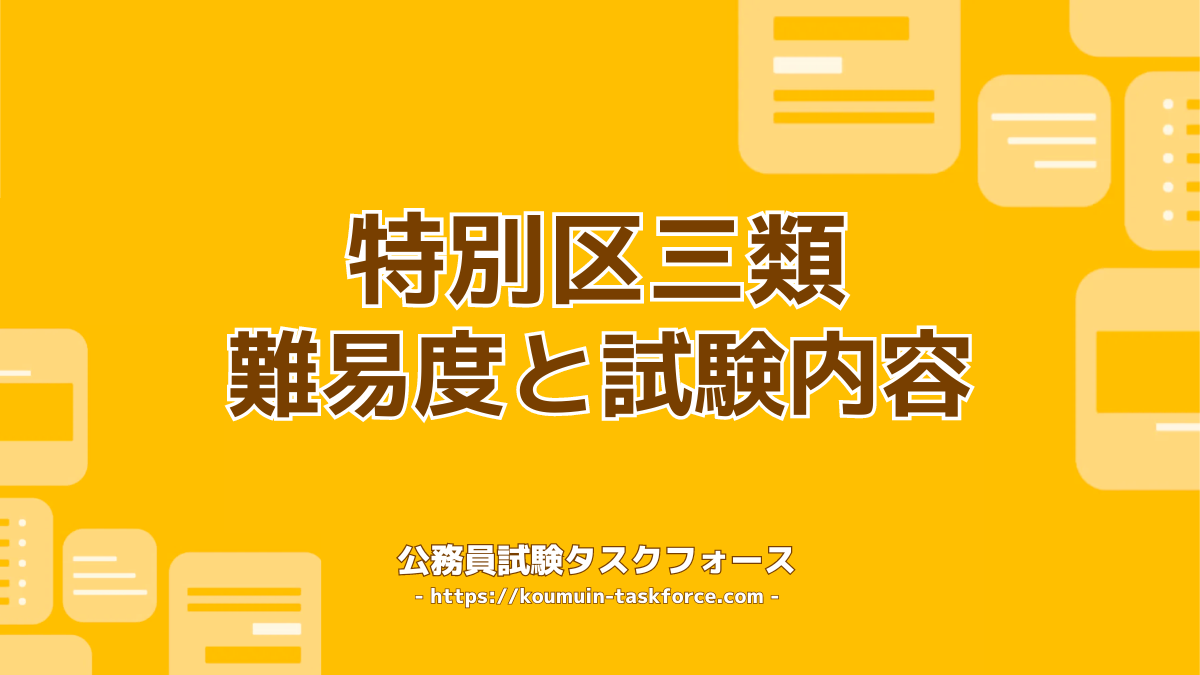「高校を卒業したら、東京特別区(東京23区)の公務員になりたい!」と思う人が最初にぶちあたる壁、特別区職員三類採用試験。
いったい、どれくらいの難易度なのでしょうか。
結論から言うと、特別区三類(高卒)採用試験は難しいです。簡単には合格できない試験なので、しっかり準備をする必要があります。
本記事では、その辺りを詳しく解説!試験内容もまとめているので、合格に向けて準備を始めましょう。
【結論】特別区三類(高卒)は難しい
結論から言うと、特別区三類(高卒)採用試験は難しいです。
理由は以下のとおり。
- 試験科目が多すぎるから
- 学力だけでは合格できないから
それぞれ解説します。
理由①:試験科目が多すぎる
一次選考の教養試験では、次の5分野19科目から出題されます。
| 分野 | 科目 |
|---|---|
| 数的処理 | 数的推理|判断推理|空間把握|資料解釈 |
| 文章理解 | 現代文|英文 |
| 社会科学 | 政治|経済|社会|倫理 |
| 人文科学 | 日本史|世界史|地理|国語|英語 |
| 自然科学 | 物理|化学|生物|地学 |
平たく言って、高校・大学入試科目数の約3倍です。これだけの科目を勉強しないといけないので、受験者の負担は相当大きいでしょう。
問題レベルは、中学校から高校までに学んだことのある内容ばかりですが、それをもう一回勉強しないといけないので簡単ではありません。
やみくもに勉強を始めるのではなく、出題傾向を理解して効率よく勉強することがポイントです。
理由②:学力だけでは合格できない
特別区三類(高卒)採用試験は就職試験です。
なので、単純な学力だけでなく、多角的な能力(公務員としての適性・資質や人間性、コミュニケーション能力など)も併せて合格者を決定します。
単純に筆記試験の点数を取れば合格できるものではなく、面接・作文などによる人間性が最重視されるため、努力がそのまま結果に結びつかない難しさがあるのです。
筆記試験の点数だけで合否が決まる高校・大学入試や資格試験とは違い、単に知識を詰め込んでいるだけでは合格できないことを意識し、どの試験科目もバランスよく対策しましょう。
特別区三類(高卒)の試験内容
特別区三類(高卒)の試験内容は大きく「筆記試験」と「面接試験」に分類できます。
選考は段階式で行われ、まず一次選考で受験者を篩にかけ人数を絞ります。その後、一次選考の合格者を対象に二次選考を行い最終合格者を決定するという流れです。
試験内容は次のとおり。
| 一次試験 | 教養試験 |
|---|---|
| 作文試験 | |
| 二次試験 | 口述試験 |
教養試験
教養試験は、一般知能(計算力や読解力を測る科目)と、一般知識(これまでの基礎学力を測る科目)で構成される筆記試験です。
| 試験時間 | 120分 |
|---|---|
| 問題数 | 50問 |
| レベル | 高校卒業程度 |
| 出題形式 | 五肢択一式 |
| 解答方式 | マークシート |
出題科目の多くは、中学校から高校までに学んだ内容ばかりです。しかし、5分野19科目もあるため、なんとも厄介な試験といえるでしょう。
| 分野 | 科目 |
|---|---|
| 数的処理 | 数的推理|判断推理|空間把握|資料解釈 |
| 文章理解 | 現代文|英文 |
| 社会科学 | 政治|経済|社会|倫理 |
| 人文科学 | 日本史|世界史|地理|国語 |
| 自然科学 | 物理|化学|生物|地学 |
やみくもに勉強を始めるのではなく、出題傾向を理解して効率よく勉強することがポイントです。
作文試験
作文試験は、自分の考えや主張を論理的に説明する文章形式の試験です。
筆記試験では判断できない、論理的思考力や読解力、人間性などを総合的に測ることを目的としています。
| 試験時間 | 80分 |
|---|---|
| 問題数 | 1題 |
| 文字数 | 600~1000字 |
| 評価基準 | ・内容 ・表現 ・文字 |
作文は、自分では文章が書けると思っていても、意外に書けなかったり、書けた(気になった)としても課題に対してまったく十分な解答にはならないことはよくあります。
勉強すればしただけ成果が見える筆記試験とは違い、客観的な評価(添削してもらうこと)でしか習熟度がわからないため、なんとも厄介な試験といえるでしょう。
毎年、作文で評価がもらえずに不合格となる受験者は一定数いるので、早めに準備をしてください。
口述試験(面接)
口述試験とは、志望動機や自己アピールなどを問うことで、あなたが特別区(東京23区)の職員として相応しいかどうかを評価・判断する面接試験のことです。
| 試験時間 | 30分 |
|---|---|
| 面接官 | 3人 |
| 形式 | 個人面接 |
間違いのない回答を目指すことも重要ですが、あまりマニュアルに頼るのではなく、それ以上に自分らしさや公務員への熱意をアピールできるように準備していきましょう。
特別区三類(高卒)に関するFAQ
最後に、特別区三類(高卒)でよくある質問(FAQ)を紹介します。
以上、特別区三類(高卒)の難しさと試験内容についてでした。
この記事が少しでもお役に立てたら幸いです。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました!