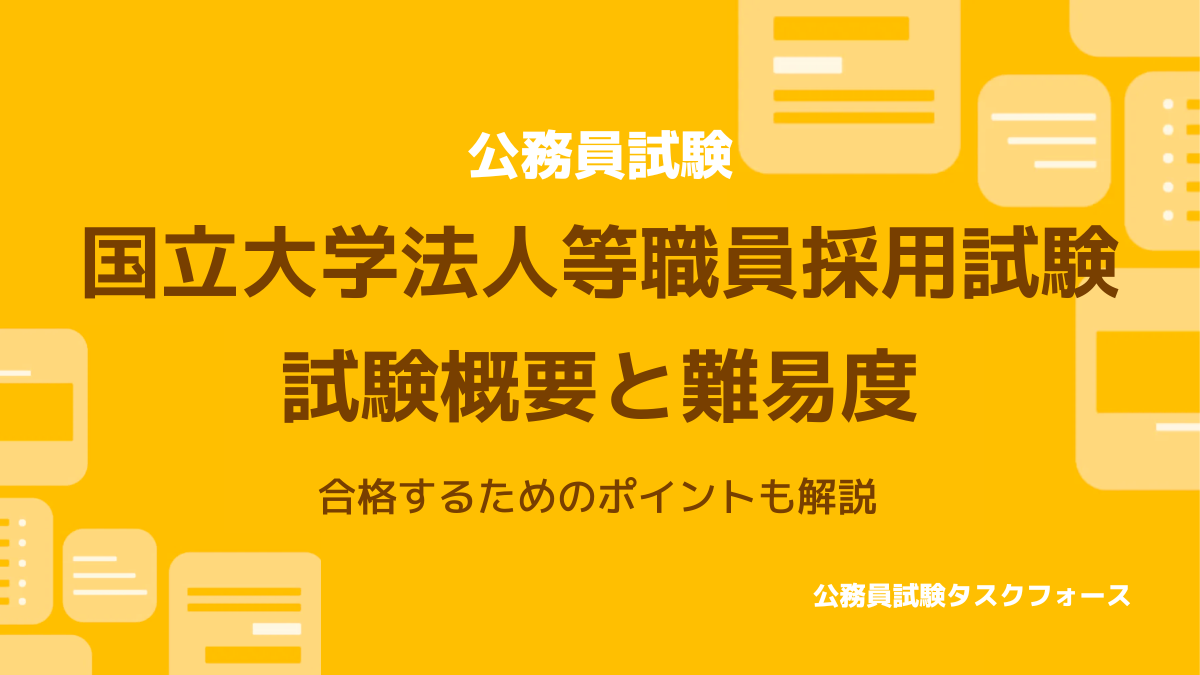-150x150.jpeg) 悩んでいる人
悩んでいる人国立大学法人等職員採用試験の難易度はどれくらいなの?合格するにはどうすればいいか教えてほしい。
こんなお悩みを解決できる記事を書きました!
結論からいうと、問題レベルやボーダーラインから考えれば難易度はたいしたことないです。
とはいえ、簡単に合格できるような試験ではありません。そこは勘違いしないようにしてください。
そこで本記事では、「これから国立大学の職員を目指したい」「受験勉強を始めたばっかり」という人を対象に、国立大学法人等職員採用試験員の難易度や難しさを解説します。
試験傾向や対策ポイントも紹介しているので、ぜひ参考に受験勉強を始めてみてくださいね。
国立大学法人等職員採用試験とは?概要まとめ
国立大学法人等職員採用試験とは、国立大学をはじめ、大学共同利用機関や国立高等専門学校を含む一部の独立行政法人と放送大学の職員を募集する試験です。
試験は全国7つの地区(北海道、東北、関東甲信越、東海・北陸、近畿、中国・四国、九州)に分けて行われ、一次試験に合格した人は点数が高い順に『採用候補者リスト』に登録されます。
この「採用候補者リスト」を参考にして、大学・機関ごとに二次選考を行い、最終合格者を決定するという流れ。



要するに大学共通入試テスト(旧センター試験)のような感じですね。一次は全員同じ、二次は希望する大学・機関を受験する。
まずは簡単に試験概要を紹介します。
※2022年のデータです。
主な採用大学(機関)
| 地区 | 大学・機関等 |
|---|---|
| 北海道 | 北海道大学、北海道教育大学、室蘭工業大学、小樽商科大学、帯広畜産大学、旭川医科大学、北見工業大学 |
| 東北 | 弘前大学、岩手大学、東北大学、宮城教育大学、秋田大学、山形大学、福島大学 |
| 関東甲信越 | 茨城大学、筑波大学、筑波技術大学、宇都宮大学、群馬大学、埼玉大学、千葉大学、東京大学、東京医科歯科大学、東京外国語大学、東京学芸大学、東京農工大学、東京藝術大学、東京工業大学、東京海洋大学、お茶の水女子大学、電気通信大学、一橋大学、政策研究大学院大学、横浜国立大学、総合研究大学院大学、新潟大学、長岡技術科学大学、上越教育大学、山梨大学、信州大学 |
| 東海北陸 | 富山大学、金沢大学、北陸先端科学技術大学院大学、福井大学、岐阜大学、静岡大学、浜松医科大学、名古屋大学、愛知教育大学、名古屋工業大学、豊橋技術科学大学、三重大学 |
| 近畿 | 滋賀大学、滋賀医科大学、京都大学、京都教育大学、京都工芸繊維大学、大阪大学、大阪教育大学、兵庫教育大学、神戸大学、奈良教育大学、奈良女子大学、奈良先端科学技術大学院大学、和歌山大学 |
| 中国四国 | 鳥取大学、島根大学、岡山大学、広島大学、山口大学、徳島大学、鳴門教育大学、香川大学、愛媛大学、高知大学 |
| 九州 | 福岡教育大学、九州大学、九州工業大学、佐賀大学、長崎大学、熊本大学、大分大学、宮崎大学、鹿児島大学、鹿屋体育大学、琉球大学 |
補足ですが、地域を跨いでの受験はできません。ですので、自分が働きたいと思う地域を受験してください。



東京大学の職員になりたいと思ったら関東甲信越を受験しないといけません。近畿地域で受験しても意味がないってことです。
受験資格(年齢制限)
学歴は関係ないので、高卒、専門・短大卒の人でも受験できます。
試験日程
| 流れ | 日程 |
|---|---|
| 出願受付 | 2022年5月11日~25日 |
| 一次試験 | 2022年7月3日(日) |
| 合格発表 | 2022年7月21日(木) |
| 二次試験 | 7月下旬~※機関ごとに異なる |
| 最終合格 | 8月中旬~※機関ごとに異なる |
一次試験は全地区同じ日に実施されますが、二次試験以降の詳細は、一次試験合格発表後に行われる説明会などで大学ごとに公表されます。
したがって、一次試験に合格しても積極的に行動しなければ二次選考を受けれないので注意が必要です。
実施状況(倍率)
| 実施年度 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 2018 | 28,677 | 7,040 | 4.1 |
| 2019 | 26,358 | 6,668 | 4.0 |
| 2020 | 23,618 | 6,545 | 3.6 |
| 2021 | 23,794 | 6,869 | 3.5 |
| 2022 | 22,604 | 7,452 | 3.0 |
なお、地域によって倍率は異なるので、どこでもいい人は倍率の低い地域を狙うのもアリですね!
詳しくは以下の記事を参考にしてください。
試験内容
- 教養試験(必須)
- 面接試験(必須)
- 論文試験 など
一次試験に『教養試験(全国統一)』が実施されます。これにクリアできれば二次試験(各大学・機関によって異なる)です。
最終合格するには筆記と面接の両方で点数を取ることが重要なので、いずれかの試験に偏った対策をするのではなく、計画を立ててバランスよく対策しましょう。
国立大学法人等職員採用試験の難易度は?
国立大学法人等職員採用試験は簡単だけど、難しい…そんな試験です。
理由は以下のとおり。それぞれ解説します。
- 試験問題は中学~高校レベル
- ボーダーラインは7割程度
- 二次選考はヤバい
試験問題は中学〜高校レベル
国立大学法人等職員採用試験の教養試験(筆記)は、あなたが今までに勉強してきた内容が試験範囲です。
なので、高校までにきちんと勉強してきた人からすれば、それほど難しいわけではありません。
たとえば、次はメイン科目の一つである数的推理の問題です。
.png)
.png)
流水算という単元で、中学入試でよく出るような問題です。
算数、数学が苦手な人は少し悩むかもしれませんが、少し勉強すれば思い出すのではないでしょうか。
たまに大学入試レベルの問題も出ていますが、多くは中学〜高校入試ぐらいの問題です。
合格ラインは7割程度
採用者数や問題レベルによって変動しますが、7割程度あれば筆記試験をパスできています。
資格試験や大学入試みたいに高得点(9割〜)が必要なら難しいと思います。でも7割くらいであれば、何とかなりそうですよね。



僕自身、26/40問の正解で最終合格しているので、そんなにボーダーは高くないです。
二次選考はヤバい
二次選考以降は各大学・機関ごとに行われるので、倍率はハンパないくらい高いです。
たとえば、結果を公表している北海道教育大学の最終倍率は13.0倍でした。
| 実施年度 | 受験者数 | 合格者数 | 最終倍率 |
|---|---|---|---|
| 2020 | 129 | 6 | 21.5 |
| 2021 | 104 | 8 | 13.0 |
努力しただけ合格率を上げられる筆記試験とは違い、面接試験は第三者の評価が大きく関わってくるから数値以上に難度高め。
少しでも合格率を上げるためには、最近の試験は人物重視であることを理解して、早めに対策をはじめることが大事です。



実際に104人受けて96人は落ちているわけですからね。これが国立大学法人等職員採用試験の真の難しさといえるでしょう。
国立大学法人等職員採用試験の対策ポイント
確実に合格する方法はありませんが、少しでも合格率を上げるポイントならあります!
それが以下の4つです。
- スキマ時間を有効活用する
- モチベーション維持
- 出題傾向を理解して勉強する
- 面接対策を試験日の2ヵ月前から始める
スキマ時間を有効活用する
始めにこれを伝えておかなければいけません。
とにかく大切なことは、時間は無限ではないということです。
じゃあ具体的にどうやって時間を捻出するの?というと、『スキマ時間を有効活用する』という結論に達します。
- 通学時間
- 学校での休み時間
- 食事の前後
- 入浴時間
- 寝る前の10分間 など
全てのスキマ時間を使うのは難しくても、自分の生活スタイルに合わせてこの中のいくつかを取り入れるだけでも十分な時間をキープできますよ。
たとえば1回20分のスキマ時間でも、1年で7,300分(約120時間)になります。これが1日の中で3回(朝、昼、夜)繰り返されるだけで、年間365時間も勉強できることになりますよね。



最終合格までに必要な勉強時間は600時間程度なので、スキマ時間だけでも6~7割ぐらいの勉強ができてしまうのです。
モチベーション維持
対策はやることが多いので…まぁ、シンドイです。
合格するために必要な勉強時間は過去のデータから600時間ほど。1日2時間の勉強を約1年間続けるようなものです。
合格目標「600時間」の勉強計画
| 1日の勉強時間 | 600時間に到達するまでの日数 |
|---|---|
| 2時間 | 300日(約10ヶ月) |
| 3時間 | 200日(約7ヶ月) |
| 4時間 | 150日(約5ヶ月) |
実際、合格を目指して勉強を始める人は多いですが、途中で挫折する人も相当多いです。100人いて30〜50人ぐらい、半分はいなくなります。
モチベーションを長期間保ちながら筆記対策も面接対策もする必要があるため、相当な覚悟が求められます。
想像してみてください、周囲が遊んでいる中で自分だけ勉強漬けの毎日、飲み会や合コンの誘いをシャットアウトしながら勉強に集中して高いパフォーマンスを維持しなければならないのです。



同じ志をもつ仲間を集めたり、合格後の姿を想像したりしてモチベーション維持を図ることが大事!
出題傾向を理解してから勉強する
二次試験(面接)の難度が高いわけですが、時間の多くは筆記対策に充てなければいけません。
教養試験の問題レベルは大したことありませんが、科目数・出題範囲が膨大なんですよね…。なので、点が取れるまで時間がかかりますし、やり方によって差がつきやすいです。
科目・範囲ともに広範な教養試験を攻略するには、出題傾向をきちんと理解することがポイント!
》教養試験の対策方法を以下の記事で解説しています。参考にしてください。
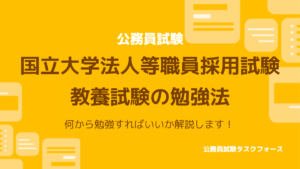
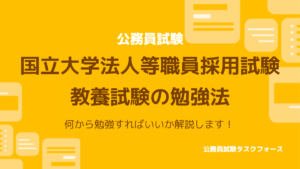
面接対策を試験日の2ヵ月前から始める
「筆記」よりも「人物(面接や論文)」の方が評価されます。
そのため筆記試験の勉強だけに時間を費やしても最終合格できませんし、今まで面接を受けたことのない初心者が合格基準に達するには、繰り返し練習する必要があるため、かなりの時間が必要です。
すでに面接でA、B評価をもらえる人なら一次試験が終わってからでも十分間に合うかもしれませんが、面接に自信を持てない人がマネすると確実に落ちてしまいます。
面接試験で評価を得るには準備が必要です。長所短所を考えたり、志望動機を考えたり…と、かなり時間がかかりますよ。
使える時間は限られているので、早めに面接対策もやってくださいね。
以上が、国立大学法人等職員採用試験の合格率を上げる方法です。
まとめ:国立大学職員の難易度は高いけど独学でも対策可能
本記事では、国立大学法人等職員採用試験の難易度や合格のポイントを解説しました。
筆記試験だけで考えれば、そんなに難しくないです。試験問題は中学〜高校レベルですし、倍率も3倍程度ですからね。
しかし、合格するのは簡単ではありません。本番は二次試験だからです。
「これをやれば確実に合格できる」という方法はありませんが、「効率よく対策するために意識するポイント」はあります。
具体的には以下の4つ。
- スキマ時間を有効活用する
- モチベーション維持
- 出題傾向を理解して勉強する
- 面接対策を試験日の2ヵ月前から始める
このようなポイントを踏まえて対策できれば短期間でも十分に合格を狙えます!
小難しい話になりましたが、要は、対策は難しいけど効率よく勉強すれば大丈夫だよ!ってことです。焦る必要はないので、やれることから少しずつやっていきましょう。
この記事が少しでもお役に立てたら幸いです。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました!