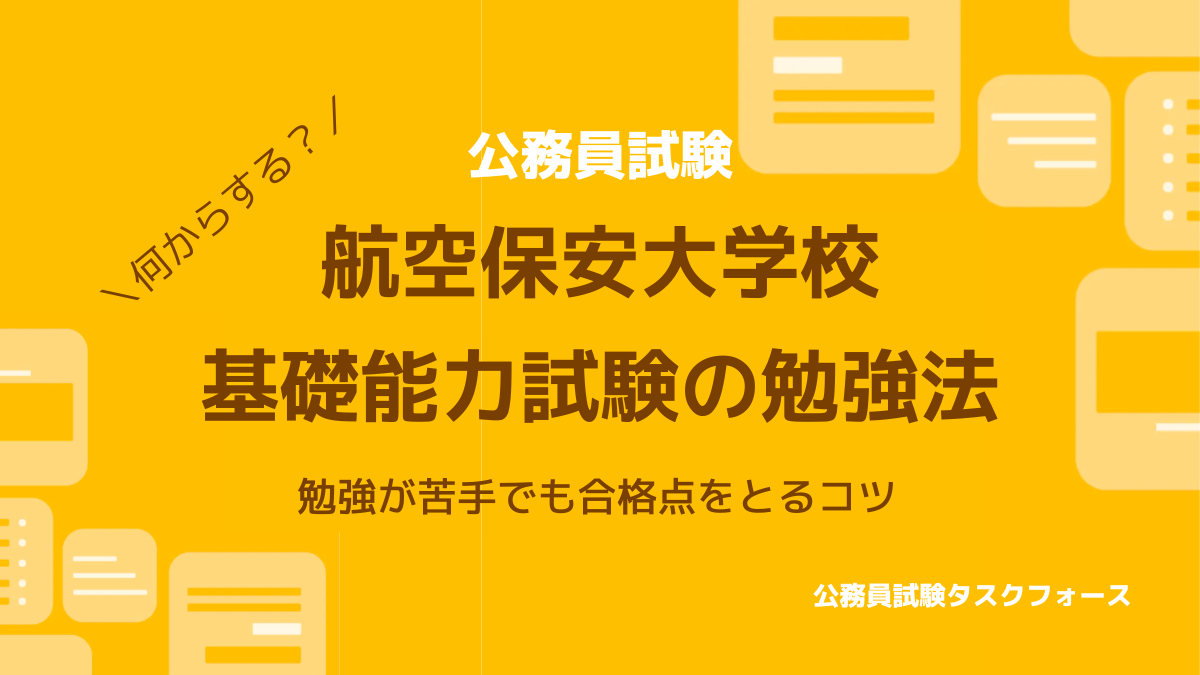航空保安大学校の一次試験で実施される基礎能力試験。
初めて受験するうえで、どんな試験科目が出ているのか気になるのではないでしょうか。
そこで今回は、航空保安大学校の基礎能力試験に関する下記内容を紹介します。
この記事でわかること
- 基礎能力試験の科目
- 基礎能力試験の傾向
- 基礎能力試験の勉強法
- 基礎能力試験の勉強効率をアップする裏技・ポイント
「基礎能力試験はどんな科目・傾向なのか」「効率的な勉強方法が知りたい」という方は、ぜひ参考にしてください。
 えもと
えもと過去10年間の出題範囲をまとめたデータを次の記事で公開しています。手っ取り早く傾向が知りたい方は活用してください。
【航空保安大学校】基礎能力試験とは?
基礎能力試験とは、航空保安大学校学生採用試験の一次選考において行われる筆記試験の一つです。
航空管制官(公務員)として働くうえで必要な、基礎学力(思考力・判断力や一般教養)がどれくらい備わっているかを測る目的があります。
基礎能力試験の概要
| 試験時間 | 90分 |
|---|---|
| 問題数 | 40問 |
| 出題形式 | 五肢択一式(マークシート) |
| レベル | 高校卒業程度 |
基礎能力試験の科目
| 一般知能 | 数的処理 | 数的推理|判断推理|空間把握|資料解釈 |
|---|---|---|
| 文章理解 | 現代文|英文|古文漢文 | |
| 一般知識 | 社会科学 | 政治|経済|社会|倫理 |
| 人文科学 | 日本史|世界史|地理|国語|英語 | |
| 自然科学 | 数学|物理|化学|生物|地学|情報 |
- 情報科目は2024年度から1問出題されます。
このように、中学~高校までに学んだ内容から多く出題されるので、科目の多い大学入試共通テストと僕は思っています。
共通テストとの大きな違いは、科目選択の有無です。
たとえば共通テストであれば、社会なら日本史か世界史、理科なら物理か生物のように、受験に必要な科目を選択して試験を受けられます。しかし、基礎能力試験では、全科目から出題があるのです。
つまり、社会なら日本史も世界史も、理科なら物理も生物もすべて勉強しないといけません。
これが公務員試験の面倒な部分であり、航空保安大学校が難しいといわれる所以です。
【航空保安大学校】基礎能力試験の出題傾向
航空保安大学校の基礎能力試験について、出題傾向を解説します。
数的推理
数的推理は、思考力や計算力を測る科目です。例年、4〜5問の出題があります。
| 分野 | 主な項目 |
|---|---|
| 方程式 | 方程式、不等式、平均算・年齢算 |
| 割合 | 比、混合算、仕事算、ニュートン算 |
| 速さ | 速さ、旅人算、流水算、時計算 |
| 確率 | 場合の数、順列、確率 |
| 図形 | 多角形、円、空間計量 |
| 整数 | 整数・約数・倍数、記数法 |
| 規則性 | 数列、規則性 |
| その他 | 計算パズル、その他 |
このうち、もっとも出題率の高い分野は「確率」です。過去10年間で9回(10問)出ているため、今後も狙われる可能性が高いと言えるでしょう。
その他、方程式も頻出なので、併せて対策できるといいですね。
判断推理
判断推理は、判断力や瞬発力を測る科目です。例年、4〜5問の出題があります。
| 分野 | 主な項目 |
|---|---|
| 順序関係 | 順序関係 |
| 対応関係 | 二集合対応、多集合対応、組分け |
| 集合 | ベン図、線分図 |
| 論理 | 論理、三段論法、ド・モルガンの法則 |
| 位置関係 | 直線、平面、空間、方向 |
| 試合 | 試合数、トーナメント、リーグ戦 |
| 証言 | 証言 |
| 暗号 | 暗号問題 |
| 数量 | 数量問題、貸し借り |
| 日歴算 | 日歴算 |
| 手順 | ルール、天秤 |
| 道順 | 道順、順列 |
このうち、もっとも出題率の高い分野は「対応関係」です。過去10年間で9回(10問)出ているため、今後も狙われる可能性が高いと言えるでしょう。
その他、位置関係も同じくらい出ているので、併せて対策するといいですね。
空間把握
空間把握は、空間認識力や図形の理解を測る科目です。例年、2問程度出ています。
| 分野 | 主な項目 |
|---|---|
| 平面図形 | 等積図、パズル |
| 折り紙 | 図形の折り方、折り紙 |
| 軌跡 | 多角形の軌跡、円の軌跡 |
| 立体図形 | 正多面体、立体構成 |
| 展開図 | 正多面体の展開図、サイコロ |
| 投影図形 | 投影図、陰影 |
| 切断図形 | 切断図、切断面の計算 |
| 回転移動 | 回転体、回転と移動 |
| 経路 | 最短経路、一筆書き |
このうち、もっとも出題率の高い分野は「平面図形」です。過去10年間で8回(8問)出ているため、今後も狙われる可能性が高いと言えるでしょう。
その他、展開図もよく出ているので、併せて対策してください。
資料解釈
資料解釈は、グラフや表から条件に当てはまる設問を選ぶ科目です。例年、2問程度出ます。
| 分野 | 主な項目 |
|---|---|
| 数表 | 表計算 |
| グラフ | グラフ、データ |
| 複合 | 数表とグラフ |
どちらの分野からもよく出ていますが、比較すると数表の方がよく出ています。
たまに、複合問題も出ているので、どちらにも対応できるように準備しましょう。
文章理解
文章理解は、300〜400字程度の文章を読んで趣旨把握や内容把握を行う科目です。例年7問出ています。
| 分野 | 主な項目 |
|---|---|
| 現代文 | 趣旨把握・内容一致、空欄補充、文章整序 |
| 英文 | 趣旨把握・内容一致、空欄補充、文章整序 |
| 古文・漢文 | 趣旨把握・内容一致、空欄補充、文章整序 |
現代文も英文も10年連続で出ているので、対策は必須です。とくに、現代文は趣旨把握・内容一致以外からも出題があるので、接続詞や助詞などの知識も必須。
古文・漢文は交互に出ています。2023年度は漢文だったので、2024年度は古文からの出題が濃厚です。
社会科学
中学校〜高校で学んだ基礎学力を測る科目です。例年6問ほど出ています。
| 分野 | 主な項目 |
|---|---|
| 政治 | 日本国憲法、統治機構、政治学、国際政治 |
| 経済 | 市場経済、日本経済、国民経済、国際経済 |
| 社会 | 労働問題、社会保障、人口問題、現代社会(時事) |
| 倫理 | 西洋思想、中国思想、日本思想 |
このうち、もっとも出題率の高い分野は「政治」です。とくに、統治機構に関する問題は過去10年間で7回(8問)出ていることから、今後も狙われる可能性が高いといえるでしょう。
その他、経済は国民経済、社会は労働問題、倫理は西洋思想が頻出です。
人文科学
中学校〜高校で学んだ基礎学力を測る科目です。例年9問出ていましたが、2024年から8問に減ります。
| 分野 | 主な項目 |
|---|---|
| 日本史 | 原始・古代、中世、近世、近・現代、通史 |
| 世界史 | 西洋史、東洋史、現代史 |
| 地理 | 地図、人類と環境、生活と産業、地誌 |
| 国語 | 漢字、四字熟語、ことわざ、現代文法 |
| 英語 | 文法、英単語 |
このうち、もっとも出題率の高い分野は「国語」です。とくに、四字熟語に関する問題は過去10年間で7回で出ていることから、今後も狙われる可能性が高いといえるでしょう。
その他、日本史は近・現代、世界史は西洋史全般、地理は人類と環境、英語は文法がそれぞれ頻出です。
自然科学
中学校〜高校で学んだ基礎学力を測る科目です。例年5問の出題ですが、2024年から情報(1問)が追加されます。
| 分野 | 主な項目 |
|---|---|
| 数学 | 数と式、二次関数・方程式、図形、三角比、数列、微分法 |
| 物理 | 速度、力、熱、波動、電磁気 |
| 化学 | 物質の構成、化学結合、化学反応式、金属元素、有機化合物 |
| 生物 | 細胞、遺伝、恒常性、植物と動物、生命の集団 |
| 地学 | 地球の構造、地殻の構成、大気の運動、太陽系と宇宙 |
| 情報 | 情報知識、PC用語、プログラミング |
このうち、もっとも出題率の高い分野は「数学」です。とくに、二次関数・二次方程式に関する問題は過去10年間で6回(6問)出ていることから、今後も狙われる可能性が高いといえるでしょう。
その他、物理は全範囲、化学は中和、生物は恒常性、地学は地殻の構成が比較的よく出ています。
【航空保安大学校】基礎能力試験の対策方法
航空保安大学校の基礎能力試験を効率よく対策(勉強)するには、次の手順を踏みましょう。
勉強する科目に優先順位をつける
まずは、どの科目から勉強するのか優先順位を決めましょう。
なぜなら、全科目から均等に出題されるわけじゃないからです。
たとえば、数的推理は5~6問出ている一方で、地学や数学は1問ずつしか出ていません。どちらの科目に時間をかけて勉強するかは明白ですよね。
以下の科目別出題数一覧を参考に、どの科目から勉強していくのか決めましょう。
| 科目 | 出題数 |
|---|---|
| 数的推理 | 4 |
| 判断推理 | 5 |
| 空間把握 | 2 |
| 資料解釈 | 2 |
| 現代文 | 4 |
| 英文 | 2 |
| 古文 | 1 |
| 政治 | 2 |
| 経済 | 2 |
| 社会時事 | 1 |
| 倫理 | 1 |
| 科目 | 出題数 |
|---|---|
| 日本史 | 1 |
| 世界史 | 2 |
| 地理 | 2 |
| 国語 | 2 |
| 英語 | 2 |
| 数学 | 1 |
| 物理 | 1 |
| 化学 | 1 |
| 生物 | 1 |
| 地学 | 1 |
- 2023(令和5)年度本試験より作成
- 上記の科目別出題数は僕自身の解釈であり、公式発表されたものではありません。



まずは数的推理と判断推理、そして社会科学を優先的に勉強するといいでしょう。
出題範囲に沿って勉強する
続いて、どの分野から覚えていくのか決めましょう。
科目別の出題傾向でも解説したように、どの科目も最初から最後まで出ていないからです。
たとえば、人文科学の日本史分野では、「第1章 原始・古代」の出題率は0%、一方で近世以降は7年連続の出題となっています。


- 上記は僕自身の解釈であり、公式発表されたものではありません。
同じ労力をかけるなら、最初(第1章 原始・古代)から勉強するよりも、頻出である分野から勉強した方が効率的ですよね。
表を見てわかるように、近世前半(江戸前期)まで出題率はゼロですからね。最初から最後まで満遍なく勉強するような無駄はやめましょう。
過去問題集を使い総復習する
最後は、公務員試験の過去問題集を使いながら総復習しましょう。
ここでは、これまでに勉強した頻出度の高い科目・分野の知識定着にくわえて、スルーしてきた分野の底上げなどにも有効です。
同レベル(高校卒業程度)であれば、どの過去問題集を使ってもOKです(オススメは「過去問350シリーズ」)。
実践形式で解くよりは、選択肢ごとにどこが間違っているのか確認しながら解いていく(正文化していく)方がいいでしょう。
勉強において重要なのは先に進むことよりもどれだけ復習をしたかということです。
復習するタイミングですが、僕は勉強した箇所は3日連続で見るというルールで覚えていきました。要するにその日に解いた問題は短いスパンで3回見るというものです。
| 1日目 | 問題1〜10をやる |
|---|---|
| 2日目 | 問題1〜10を見直して、問題11〜20をやる |
| 3日目 | 問題1〜20を見直して、問題21〜30をやる… |
とくに重要なのが翌日の復習。
勉強した次の日に復習しないだけで一気に知識の定着が悪くなります。記憶の法則で有名なエビングハウスの忘却曲線でも人間の記憶力は翌日にガタ落ちすることが立証されていますからね。
最初のうちはけっこうシンドイですが、1カ月ほど続けてみれば結果が見えてくるので、反復練習を意識して勉強していきましょう。
【航空保安大学校】基礎能力試験に関するFAQ
最後に、航空保安大学校の基礎能力試験対策でよくある質問(FAQ)を紹介します。
オススメの参考書・問題集はありますか?
- オープンセサミシリーズ(セサミ)
- スーパー過去問ゼミ(スー過去)
この2冊がオススメです。
公務員予備校東京アカデミーが監修している”初心者〜中級者向け“の参考書です。
情報量が豊富でこれ1冊を覚えるだけでかなりの点数が取れます。
しかし、無駄な情報もそれなりに含まれているので出題範囲を絞って使いましょう。
過去問はどこで入手できますか?
人事院に行政文章開示請求をすることで入手できます。解説はありませんが、問題形式やレベルなどの把握には十分です。
また、次の記事でも一部の問題・解答をまとめているので、参考にしてください。
ボーダーラインは何割くらいですか?
6割(24/40問)あれば十分合格できます。
ボーダーラインは年度によって変動するため一定ではありませんが、例年6割前後で推移しています。なので、最低5割を目安に6割〜7割取れるように準備してください。
【航空保安大学校】基礎能力試験まとめ
航空保安大学校の基礎能力試験は、高校までにきちんと勉強してきた人からすればそれほど難しいわけではありません。
それなのに多くの受験者が悩んでいるのは、試験科目・範囲が膨大だからです。
事実、「科目が多くて何から勉強すればいいか分からない」という相談・お問合せが相当多いんですよね。
基礎能力試験を効率よく勉強するには、出題範囲の理解(=過去問分析)がとても重要です。必要な科目・分野に沿って勉強すれば、これまでよりずっとラクに合格点を超えるようになると僕は考えます。
合格点は5~6割程度です。そんなに高くありません。なので、闇雲に無駄な勉強をするのではなく、過去の出題傾向を軸に勉強してください。
まずは科目ごとの出題範囲を理解する。
そこから始めていきましょう!