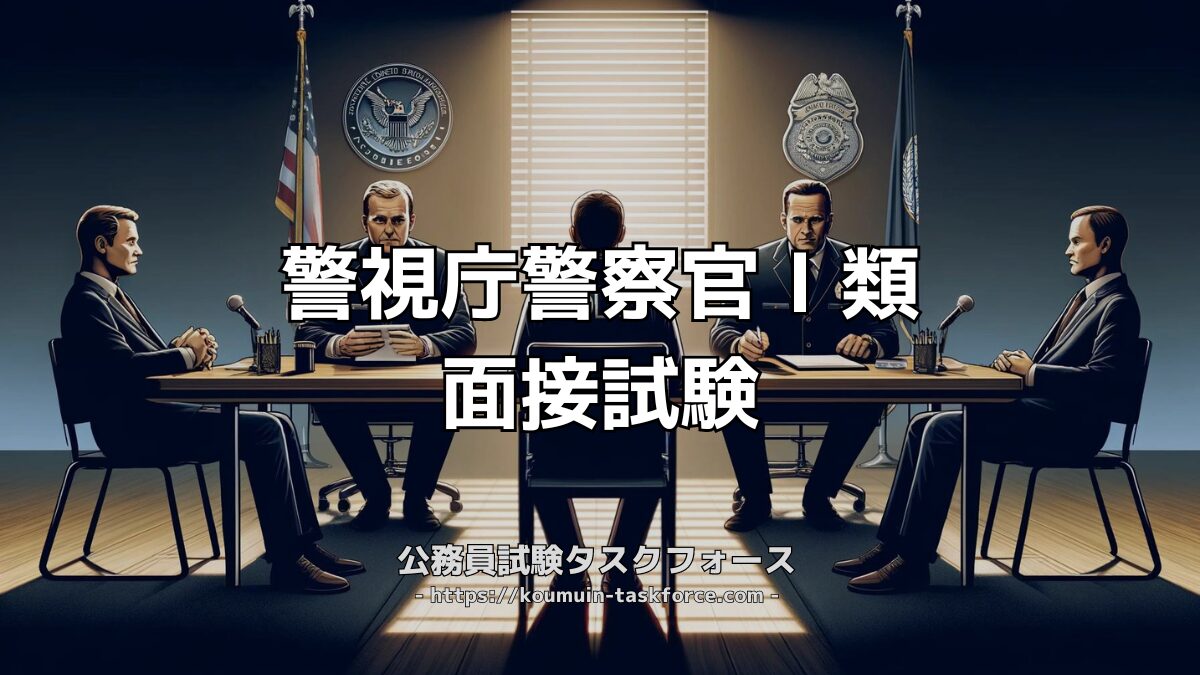本記事では、警視庁警察官採用試験1類における面接試験を徹底解説します。
「面接試験の傾向や対策方法が知りたい」「質問内容(過去問)は?」「面接カードって何?」という方は、ぜひ参考にしてください。
その他の試験内容についても下記記事で解説しています。
警視庁警察官採用試験1類の面接試験とは
警視庁警察官採用試験1類の面接試験とは、第二次選考で行われる人物面に関する試験のことです。
これまでに頑張ったことや警視庁で働きたい理由などを問うことで、あなたが警察官(公務員)として相応しいかどうかを評価・判断します。
| 実施形式 | 個人面接 |
|---|---|
| 試験時間 | 30分程度 |
| 面接官 | 3人 |
| 面接カード | あり(二次試験日に記入) |
 えもと
えもと圧倒的に面接重視です。軽視すると合格は厳しい・・・。
面接カードは、面接試験で使用される資料です。
氏名や学歴などの基本情報にくわえ、志望動機や自己PRなど、面接官が「受験者はどんな人物なのか?」を見極めるための役割があります。
二次試験当日に試験会場で作成し、そのまま提出。記入時間は30分しかないため、あらかじめ書く内容を考えておく必要があります。
面接カードの内容
- 事故・違反・停学等の処分歴
- 学歴・表彰歴の有無と内容
- 職歴・アルバイト経験
- 資格
- 自動車運転免許の有無
- 高校・大学でのスポーツ歴
- ボランティア活動の有無
- 長所、自己PR
- ゼミ・研究室の活動内容
- 過去の受験歴
- 趣味・特技
- 希望する部署とその理由
- 読書の有無と読書量、その理由
- SNSの使用状況(アカウント名記入)
- 家族構成
- 面接カードの内容は非公開です。
- 上記は、2023年度受験者からの情報提供をもとに作成しています。
実際の試験では、提出する面接カードに基づいて過去の経歴や経験、志望動機や今後の抱負など幅広く聞かれているので、わかりやすくアピールできる内容を考えておきましょう。
警視庁警察官採用試験1類 面接試験の過去問(質問)
ここでは、過去の面接試験で具体的に聞かれた質問をまとめています。
自分なりの回答を練って対策をはじめましょう!
第1回(一類)
- 自己紹介をしてください。
- 志望動機を言ってください。
⇒なぜ警視庁を志望するのですか。
⇒警視庁のイメージを言ってください。 - 長所と短所を簡潔に言ってください。
- 趣味はありますか。
⇒どのくらいやっていますか。
⇒なぜ始めたのですか。 - 語学はどのくらいできますか。
⇒これから極めたい語学はありますか。 - 友人はどれくらいいますか。
⇒友人からどのように思われていると思いますか。
⇒親友の名前と漢字を教えてください。 - 警察官になることを誰かに相談しましたか。
⇒両親はなんと言っていますか。
⇒友人はなんと言っていますか。 - 新聞は読んでいますか。
⇒なぜ読んでいないのですか。
⇒社会的なニュースはどうやって集めていますか。 - 最近気になっているニュースはありますか。
⇒なぜそのニュースが気になるのですか。
⇒そのニュースについてどのくらい調べましたか。
第2回(一類)
- 志望動機を言ってください。
⇒なぜ警察官を志望するのですか。
⇒なぜ警視庁を志望するのですか。 - 警察官としてやりたい仕事を言ってください。
- 警察官になることを誰かに相談しましたか。
⇒両親はなんと言っていますか。 - アルバイト経験はありますか。
⇒初めて給料をもらったときはどう思いましたか。
⇒初めての給料は何に使いましたか。 - 新聞はよんでいますか。
⇒どこの新聞を読んでいますか。
⇒今朝の見出しは何でしたか。 - どうしても欲しい物があるときはどうしていますか。
⇒残り1品しかなくお金がない場合はどうしますか。 - 大学の学費は誰が出しましたか。
- 交際相手はいますか。
⇒今後は作るつもりはありますか。 - 今までに最も頑張ったことは何ですか。
⇒その時の頑張りは今に活きていますか。 - 親友と呼べる友人はいますか。
⇒その友人の名前の漢字をわかりやすく説明してください。
⇒その友人は警察官になることをどう思っていますか。 - 最後に警視庁に要望することはありますか。
第3回(一類)
- 今日はどこから来ましたか。
- 迷わずに会場まで来れましたか。
- 警視庁を志望する理由を教えてください。
- 併願はしていますか。
⇒併願先の志望理由は何ですか。
⇒併願先にも合格したどちらに行きますか。 - 今までに事故や違反をしたことはありますか。
⇒交通事項が起きる原因は何だと思いますか。
⇒交通事項を防ぐために警察官としてできることはありますか。 - 自己啓発として取り組んでいることはありますか。
⇒なぜ自己啓発をしようと思ったのですか。
⇒自己啓発をして得たことはありますか。 - 気になる時事はありますか。
⇒その時事についてどう思いますか。 - 趣味はありますか。
⇒ほかに何かありますか。 - 集団生活はしたことがありますか。
⇒寮生活で不安なことはありますか。
⇒集団生活で注意することはありますか。 - 何か資格を持っていますか。
⇒その資格は警察官として役に立ちますか。 - 読書はしますか。
⇒今のおすすめは何ですか。
⇒簡単に内容を教えてください。 - 最近のニュースで気になることはありますか。
⇒普段はどのようにニュースをチェックしていますか。 - 仲のいい友人の名前は何ですか。
⇒その友人の名前を漢字で書くとどう書くのか説明してください。 - 警視庁への要望はありますか。
何を聞かれるのかがあらかじめわかっていれば、事前に備えることができます。一方で、何を聞かれるのかが不明瞭では、準備のしようがありませんからね。
なお、ここには掲載しきれなかった質問や模範回答例を次の記事でまとめています。たくさん練習したい方は、ぜひ参考にしてください。
警視庁警察官採用試験1類 面接の対策方法
警視庁警察官採用試験1類の面接対策を始めるときの手順を解説します。
定番の質問内容を把握する
まずは、面接試験で問われる定番質問を把握しましょう。
なぜなら、筆記試験のように面接試験にも傾向があるからです。
- 基本的な質問事項が多いのか
- 時事的な質問は聞かれるのか
- 専門的な(警視庁に特化した)質問はあるのか
このような傾向を把握しておけば、面接の準備を効率よく進めることができます。
たとえば、「自己PRをしてください」や「志望動機は何ですか?」のような一般的な質問が多ければ、書店に売っている参考書を読み込んで対策できます。
一方で、「数ある組織の中で警視庁を志望する理由は?」や「成人年齢の引き上げについてどう思いますか?」といった質問が多ければどうでしょうか?
このような警視庁に関連した質問や時事的な質問が多ければ、仕事内容や組織、社会情勢についても深く知っておく必要がありますよね。
無駄な時間を過ごさないためにも、よく出る定番質問に目を通し、傾向を押さえておきましょう。
模範回答を作り込む
続いて、定番質問をもとに回答を作成しましょう。
回答を作るときのポイントは、結論+理由(根拠)+具体例(体験談)のセットで考えること。
たとえば、「あなたの長所は何ですか」と聞かれたら何と回答しますか?
- 「リーダーシップが取れる」
- 「責任感がある」
- 「計画的に行動できる」
これくらいなら、少し考えれば回答できると思います。
では、なぜ「それが長所なのですか?」とか、「どんなときに長所を活かせましたか」と理由や経験を聞かれたどう回答しますか?
何も考えていなければ、スラスラ答えることはできないと思います。
しかし、面接官が一番聞きたいのは、ココ(理由や経験)なんですよね。自分の回答に対して論理的に答えられないと評価は上がらないのです。
ぜひ、時間をかけて自分自身をきちんと理解(自己分析)してください。
警視庁一類の定番質問や回答例は下記を参考にしてください。
人に話す練習をする
ある程度、話す内容を考えたら第三者に聞いてもらいましょう。
自分で考えていることを分かりやすく伝えるのは難しいからです。
僕自身、毎年多くの自己PRや志望動機を見たり、聞いたりしますが、初っ端から理解できる内容はほとんどありません。せっかく面接カードに良い内容を書いているのに、自分の言葉で伝えられずに損している人を多く見てきました。
面接は、あなたの発言内容を聞いて第三者である面接官が客観的に評価します。なので、どんなにいいことを発言しても伝わらなければ意味がないのです。
恥ずかしがらずに自分の言葉でスラスラ喋れるまで練習してください。
模擬面接は最低1回受ける
最後は、模擬面接を受けて実践力を鍛えましょう。
- 本番特有の緊張感
- 回答に困る深掘りポイント
- 客観的な評価
このように1人で面接練習をしていては気が付かない部分がたくさん発見できるからです。
練習相手は友達や家族でもいいですが、できるだけ経験者(予備校やその道のプロ)にもみてもらってください。
警視庁警察官採用試験1類の面接でよくある質問FAQ
最後に、警視庁警察官採用試験1類の面接でよく相談される質問を紹介します。
面接で落ちる人の特徴は?
- 準備不足
-
警視庁の職務内容や警察官の使命・役割などに関する知識が不足している。または、定番質問への回答が準備されていないなど、面接に十分な準備をしていないことが一番の問題です。
- 印象が良くない
-
- 機械的な受け答えしかできない
- 表情が暗い
- 声が小さい
- ハキハキ喋れない
- 視線が合わない(目をみて話せない)
これらの非言語的コミュニケーションが不適切だと、面接官に悪い印象を与えてしまい落ちる可能性が高くなります。
試験といっても、人間が人間を評価する試験ということを念頭に準備してください。
- 警察官(社会人)としての適性がない
-
- 挨拶がきちんとできない
- 正しい敬語が使えない
- 時間が守れない
このような行動は、警察官として、社会人としての適性に欠けます。とくに少し圧迫気味な質問をされて、すぐに不機嫌になったり、逆ギレしたりするのはNGです。
警察官・社会人として恥ずかしくない振る舞いをしてください。
当然、これらの不合格フラグは1人では判断できません。必ず第三者に協力してもらうことが面接で落ちないポイントと言えるでしょう。
面接カード作成のコツやポイントは?
面接カードを書くときは、次の点を意識すればOKです。
- 結論から先に書く
- 抽象的な表現は避ける
- 一文を長くしない
結論から先に書く
これ、とても重要です。
面接カードだけでなく、論文でも、面接試験でも、これからの社会人生活でも…「結論」と「根拠」を分かりやすく明確に伝えるようにしましょう。
もっとも大切なのは『結論』なので、それが面接官に伝わらないとまったく意味がないですよね。また、その根拠をシンプルに説明できないと納得してもらえません。
だから結論を先に書く!その根拠(の要約)も最初に説明しておく!
この2点を厳守するだけで、あなたの自己PRや志望動機は格段にレベルアップしますよ。



回りくどい説明や、結論がどこに書いてあるか分からない面接カードは、ただただ迷惑でしかない!
抽象的な表現を多用しない
少しでも面接官に伝わる自己PRや志望動機を書きたいのであれば、抽象的な表現を使わずに書きましょう。
たとえば「社交性」とか「協調性」などです。そもそも社交性、協調性とは?ってなりますし、だいたい使い方を間違っているケースがほとんとだからです。
抽象的な表現を使うときは、かならず簡単な〝例″を添えるなどしてわかりやすくするように心がけてください。
小難しい文章を書くよりも、シンプルでわかりやすい文章のほうが面接官からしても評価は高いのです。



文章を書くときには「中学2年生程度の子どもでもわかるように書く」ことを意識してみるといいでしょう。
一文を長くしない
自己PRや志望動機がわかりにくい人は、一文が長い(無駄な表現が多い)です。
たとえば次の文章。内容は同じですが、文章Bの方が読みやすいと思います。
私が警視庁を志望した理由は、東京都民の安全を守りたいと思ったことや昔から警察官に憧れていたこと、そしてこれまでの人生経験を存分に活かせると思ったからです。
私が警視庁を志望した理由は、東京都民の安全を守りたいと思ったからです。また、昔から警察官に憧れがあり、これまでの人生経験を存分に活かせると思ったからです。
一文が長くなると途端に読みにくくなりますし、主述の関係もわかりにくく理解が難しくなります。
また、ギッシリと一文を詰め込みすぎるのも読みにくくなる原因なので、余白を上手く使ってみてください。



接続詞「~ので」、「~だが」を使いすぎると長くなりやすいので注意!
面接試験(二次)の倍率はどれくらいですか?
二次試験倍率は4倍程度です。
一次試験倍率は1.5倍程度なので、明らかに面接重視の選考方針ですね。
筆記試験の対策はほどほどして、早めに面接対策にシフトするのが最終合格に近づくヒントと言えるでしょう。
警視庁一類の倍率は下記を参考にしてください。
面接対策を万全に行い受かる人になろう!
警視庁警察官採用試験1類に受かるには、面接試験の攻略が必要不可欠です。
面接攻略には次のステップに沿って対策することがポイント。
早い段階から定番質問や回答を作り、自分の考えをわかりやすく話す(伝える)練習を繰り返すようにしましょう。
面接対策は筆記試験よりもやることが多く、上達するまでかなり時間が必要です。できるだけ早めに手をつけて攻略していきましょう!
今回ご紹介させていただいたのはほんの一例ですが、ぜひ取り入れていただければ幸いです。
警視庁一類の定番質問や回答例は下記を参考にしてください。