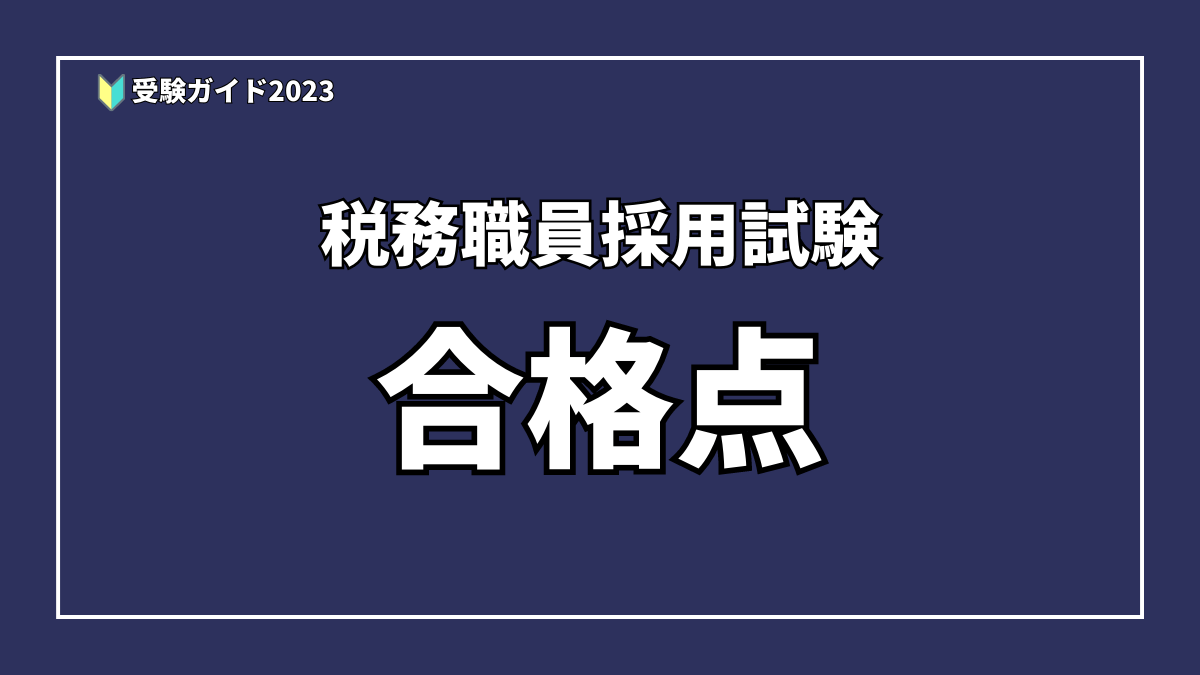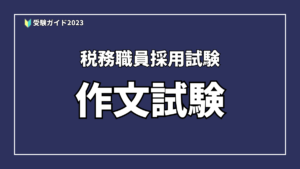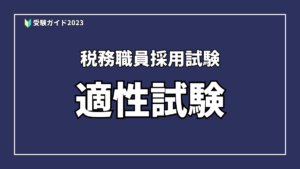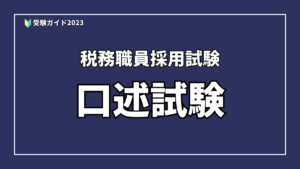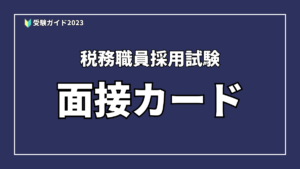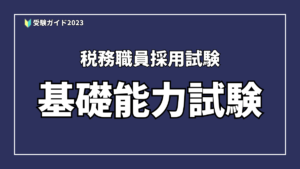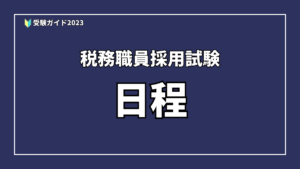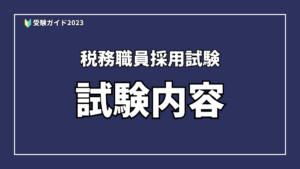- 税務職員採用試験のボーダーライン(合格点)
- 合格点を取るための勉強方法
結論からいうと、税務職員採用試験の合格ラインは6割が一つの目安になります。
というのも、選考は競争試験(合格できる人数が決まっている)なので、4割で合格できる年度もあれば、6割でギリギリってこともあるんですよね。
そこで本記事では、過去3年分の合格ラインを地域別(北海道、東北、関東甲信越、東海北陸、近畿、中国、四国、九州、沖縄)にまとめています。
合格点を取るためのポイントも解説しているので、ぜひ参考にしてくださいね。
【前提知識】税務職員採用試験 標準点の計算方法
税務職員採用試験の点数は、各試験の素点(正解数)ではなく、平均点や標準偏差を用いて算出する「標準点」として判断されます。
計算式は以下のとおり。

たとえば、以下のデータを使って計算すると、この受験者の標準点は「429.2」となります。
- 素点:22点(22/40問)
- 平均点:19.809
- 標準偏差:4.853
- 配点比率:2/4
- 素点:76点(76/120問)
- 平均点:64.311
- 標準偏差:21.612
- 配点比率:1/4
【基礎能力試験の計算式】
$$10\times\frac{2}{4}\times(15\times\frac{22-19.809}{4.853}+50)=283.9$$
【適性試験の計算式】
$$10\times\frac{1}{4}\times(15\times\frac{76-64.311}{21.612}+50)=145.3$$
ちなみに関東甲信越の最低点は363点だったので、この点数を取っていれば合格したことになります。
税務職員採用試験のボーダーライン(合格点)
ここでは、税務職員採用試験(高卒)のボーダーラインを年度別・地域別に紹介します。
得点一覧表も作成しているので参考にしてください。
得点表を見れば、標準点が何点になるのか一発でわかりますよ!
2022年(令和4年実施)
平均点等
| 項目 | 基礎能力試験 | 適性試験 |
|---|---|---|
| 満点 | 40 | 120 |
| 基準点 | 12 | 36 |
| 平均点 | 18.836 | 65.529 |
| 標準偏差 | 4.704 | 19.473 |
合格点
| 地域 | 一次試験 | 最終結果 |
|---|---|---|
| 北海道 | 375 | 531 |
| 東北 | 397 | 516 |
| 関東甲信越 | 359 | 524 |
| 東海北陸 | 343 | 481 |
| 近畿 | 327 | 481 |
| 中国 | 347 | 501 |
| 四国 | 338 | 538 |
| 九州 | 407 | 565 |
| 沖縄 | 490 | 618 |
》得点表一覧はこちら。
2021年(令和3年実施)
平均点等
| 項目 | 基礎能力試験 | 適性試験 |
|---|---|---|
| 満点 | 40 | 120 |
| 基準点 | 12 | 36 |
| 平均点 | 19.809 | 64.311 |
| 標準偏差 | 4.853 | 21.612 |
合格点
| 地域 | 一次試験 | 最終結果 |
|---|---|---|
| 北海道 | 399 | 559 |
| 東北 | 400 | 542 |
| 関東甲信越 | 363 | 531 |
| 東海北陸 | 361 | 475 |
| 近畿 | 347 | 488 |
| 中国 | 338 | 492 |
| 四国 | 378 | 550 |
| 九州 | 410 | 553 |
| 沖縄 | 528 | 644 |
》得点表一覧はこちら。
2020年(令和2年実施)
平均点等
| 年度 | 基礎能力試験 | 適性試験 |
|---|---|---|
| 満点 | 40 | 120 |
| 基準点 | 12 | 36 |
| 平均点 | 20.241 | 45.540 |
| 標準偏差 | 5.307 | 14.049 |
合格点
| 地域 | 一次試験 | 最終合格 |
|---|---|---|
| 北海道 | 376 | 554 |
| 東北 | 397 | 526 |
| 関東甲信越 | 406 | 552 |
| 東海北陸 | 340 | 463 |
| 近畿 | 327 | 472 |
| 中国 | 245 | 435 |
| 四国 | 240 | 390 |
| 九州 | 429 | 568 |
| 沖縄 | – | – |
》得点表一覧はこちら。
税務職員採用試験 合格点を取るためのコツ
税務職員のボーダーラインは5~6割なので、全科目・範囲を勉強する必要はありません。むしろ、全部に手をつけて中途半端になるよりも、必要な部分にそって効率よく勉強することがポイントです。
効率よく勉強するには、以下のポイントを意識しましょう。
- 科目ごとの配点
- 科目ごとの出題範囲
コツ①:科目ごとの配点を理解する
基礎能力試験の試験科目は多いですが、配点(問題数)は科目によって違います。勉強時間は限られているので、同じ時間を使うなら配点の高い科目に使った方が効率的です。
なので、適当に勉強を進めるのではなく、どの科目から勉強すれば点を伸ばしやすいか考える必要があります
コツ②:科目ごとの出題範囲を理解する
問題集や参考書を最初から最後まで勉強してはいけません。なぜなら、無駄な(試験に出ない)部分が多いからです。
- 数的推理の出題範囲が「速さ」だけと分かっていたら、「確率」や「仕事算」の勉強はしますか?
- 日本史の出題範囲が「江戸時代」だけだったら、「平安時代」や「鎌倉時代」の勉強はしますか?
- 物理の出題範囲が「重力」だけだったら、「電磁気」や「波動」の勉強はしますか?
しないですよね。試験に出ないので勉強するだけ時間の無駄です。
勉強ができない、どれだけ時間をかけても点数がとれない、という人は、こういった出題範囲を理解せず(理解したつもりで)勉強しています。
よく出ている分野がある一方でまったく出ていない分野も相当多いです。試験に出ない部分にどれだけ時間をかけて勉強しても点数は伸びないので注意してくださいね。
基礎能力試験の出題傾向は【独学向け】税務職員の基礎能力試験とは?勉強法と出題傾向を解説でまとめています。ぜひ、参考にしてください。
まとめ:税務職員の合格ラインを意識して対策しよう
今回は税務職員採用試験のボーダーラインと効率的な対策方法を解説しました。
ボーダーラインは採用人数や問題レベルによって変動するため確かなことはいえませんが、合格者の情報データから5〜6割程度だと推測できます。
高得点を目指して無駄な勉強をするよりも、安定して6割を取れるように準備することが大切です。
効率よくボーダーを取るために必要なポイントは次の2つ。
- 科目ごとの配点
- 科目ごとの出題範囲
とにかく試験科目は多いので、きちんと出題傾向を理解して効率よく勉強することがポイントになります。
やり方を間違えずに正しい道筋(出題傾向)を知り、それに沿って問題を解く。
そうすれば、科目・範囲ともに膨大な教養試験の勉強は、これまでよりずっとラクに合格点を超えるようになると僕は考えます。
まずは科目ごとの出題範囲を理解する。そこから始めていきましょう!
\ 効率よく「受かる対策」を始めよう /
※タップすると税務職員の概要と対策方法の記事に移動できます。