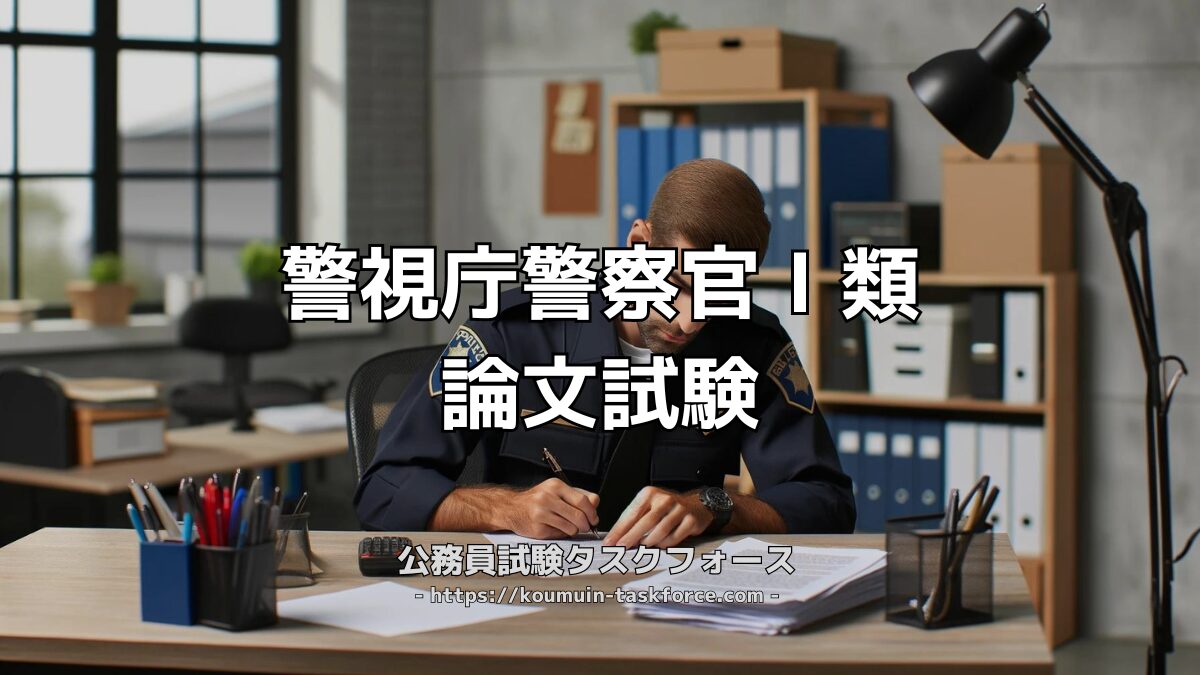本記事では、警視庁警察官採用試験1類の論文テーマ(過去問)を紹介します。
文字数や対策方法も解説しているので、ぜひ参考にしてください。
その他の試験内容はこちらで解説!
警視庁警察官採用試験1類の論文テーマ(過去問)
警視庁警察官採用試験1類の論文テーマ(2023年~2010年)を紹介します。
- 第1回(4月試験)のテーマです。
2023(令和5)年度
これまで最も苦労した経験に触れ、そこから学んだことをどのように警察官の仕事に活かしていきたいか述べなさい。
2022(令和4)年度
これまであなたが人との関わりから学んだことについて触れ、今後それを警察官の仕事にどのように活かしていきたいか述べなさい。
2021(令和3)年度
現在、自らの成長に必要なものを理由とともに述べた上で、今後、その成長に向けてどのように努力し、警察官として自らの能力を発揮していきたいか述べなさい。
2020(令和2)年度
努力して困難に打ち勝った経験と、そこから得たことをどのように警察官として活かしていきたいか述べなさい。
- コロナによって第1回が中止のため、第2回(9月試験)のテーマを掲載しています。
2019(令和元)年度
警視庁警察官という職業についてあなたの考えを述べた上で、警察官になることに対する自信と不安について述べなさい。
2018(平成30)年度
このラインより上のエリアが無料で表示されます。
失敗に学び成長した経験と、その経験を警察官としてどのように活かしていきたいか述べなさい。
2017(平成29)年度
過去にストレスやプレッシャーを感じた事と、その対処法について触れ、今後、警察官としてそれをどのように活かしていきたいか述べなさい。
2016(平成28)年度
警察官が持つべき倫理観とは何か。あなたの経験に基づき述べた上、目指す警察官像について及びなさい。
2015(平成27)年度
あなたが警察官になって守りたいものとは何か、その理由を具体的な経験から述べなさい。
2014(平成26)年度
警察が社会秩序の維持の為にすべきこととは何か、あなた自身がルールを守る必要性を感じた具体的経験から述べなさい。
2013(平成25)年度
あなたが失敗した経験から学んだことを具体的に述べ、その経験を警察官の仕事にどのように活かしていきたいか述べなさい。
2012(平成24)年度
あなたはこれまで人から信頼されるために、どのように行動してきたか、警視庁警察官としてどのように行動していこうと考えているか実体験を交えて述べなさい。
2011(平成23)年度
あなたがこれまで人のために行動して得たものは何か、それを警視庁警察官としての仕事にどのように活かせるか述べなさい。
2010(平成22)年度
過去に達成感を得た経験と、その経験を警視庁警察官としてどのように活かしたいか述べなさい。
警視庁警察官採用試験1類の論文対策でよくある質問
警視庁警察官採用試験1類の論文対策でよくある質問をまとめています。
これからの論文対策で必要な情報ばかりなので、ぜひ参考にしてください。
論文の試験時間は?
論文の試験時間は80分(1時間20分)です。
制限時間内で文章を適切に構成し、要点を明確に伝えることが重要です。また、普段から時間配分を意識して書く練習をしてください。
論文の文字数制限は?
論文の文字数は1,000字以内です。
文字数は少なすぎると減点、もしくは採点されない場合もあるため注意してください。
知識や語彙が乏しいと多くの文字を書くのは難しいので、普段から語彙力も増やしておくといいでしょう。
論文は何文字くらい書けばいいですか?
論文は9割以上書きましょう。
文字数は誰が見ても一発でわかる評価基準なので、極端に文字数が少ないと減点もしくは採点不可の判定を受けることになるんですよね。
下限(おそらく600字)程度なので、下回らないように気をつけてください。
論文の配点は?
論文の配点は非公開です。
しかし、受験者からの報告や開示データ、他県の警察官採用試験から推測すると以下のようになります。
- 教養試験:15%
- 論文試験:20%
- 国語試験:5%
- 面接試験:40%
- 体力検査:20%
このようにかなり重要だとわかるはずです。実際、教養試験の点数が低い方が合格していることからも論文の重要度は高いと言えるでしょう。
論文対策はいつから始めればいいでしょうか?
論文対策は試験日の3ヶ月前から始めましょう。
論文を正しく書けるようになるには、以下の知識を身につける必要があるからです。
- 課題の把握力(読解力)
- 文章構成力
- 表現力
- 語彙力
- 漢字(日本語)の知識
これらの力は短期間で身につくものではありません。語彙力や漢字の知識くらいなら1ヶ月でも何とかなりますが、他の力を短期間で身につけるのは厳しいです。
①書き方を勉強する
↓
②実際に書いてみる
↓
③添削を受けて、弱点を知る
↓
④何度か繰り返す(最低でも3回)
こういった順番で勉強することになるので、やはり最低でも3ヶ月は必要だと思って学習スケジュールを組んでみてください。
論文対策は下記記事で詳しく解説しています。
論文対策でオススメの参考書は?
『よくわかる! 公務員試験のための論作文術シリーズ』がオススメです。
模範解答をもとに良い例、悪い例を学べます。
最初は模範解答を参考にしながら「良い型」を身につけてください。最終的には模範解答をそのままコピーするのではなく、自分なりの表現方法やアイデアを加えてオリジナリティを出せるようにしましょう。
論文で落ちる人の特徴は?
論文で落ちる人は、答案を書いたら書きっぱなしの人です。
論文試験で落ちる人ほど、書いたら書きっぱなしってことが多いんですよね…。
論文を書いて誰にも見せないというのは、問題を解いても答え合わせをしないのと同じことです。
正解不正解がわからないまま対策を続けても成績は伸びないので、書いた答案は必ず添削してもらいましょう。
学生なら学校の先生、社会人なら予備校やオンライン添削サービスなど、方法はたくさんありますよ。
論文添削サービスを下記記事でも紹介しています。
以上、警視庁警察官採用試験1類の論文についてでした。
この記事が少しでもお役に立てたら幸いです。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました!